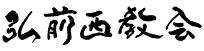宣教
2024-07-14
7月14日「神に不可能なこと」
列王下13:22~23 ローマ11:29~36
マリアに天使は、「神にはできないことは何一つない」(ルカ:1:37)とイエス様を身ごもることを告げます。「神に不可能なことはない」ことを聖書は語り続けています。私もそのように教えられ、信じるようにしてきましたし、伝えてきました。
しかし、聖書は、一方で「神に出来ないことがある」ことをはっきりと伝えることに気づきました。それは、『人間を見捨てること』です。「ヨハネ3の5」としてよく知られている、「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。」これが神様の御心であることを、わたしたちは知っています。
神様は、「いつ、どんな時」にもわたしたちを愛し、わたしたちの名前を呼んでおられるということを信じることが、わたしたちの信仰です。
「神様に不可能などない!」と信じることとは、どんなことでしょうか?それは、「神様はわたしたちを見捨てることができない」ことを信じることでこれが、「神は愛である」ということです。
「神の賜物と招きとは、取り消されないものなのです。」とある通りです。神の不可能の上に、わたしたちの信仰は守られているのです。ハレルヤ!
2024-07-14
7月7日「神が報いてくださる」
マタイ6:1~4
人に評価されること、これはとても気持ちの良いものです。主イエスは、町の至る所でそのように評価されている人たちを見かけられたのでしょう。「あの人はすごい人だ」という賞賛の声こそ、彼らが受けている報いだとおっしゃったのです。
主は善行を否定されたのではありません。良いことをして評価される、という常識を超えて、さらに豊かな世界を見せようとされたのです。それは、天の父なる神が報いを与えてくださる、という世界です。
あなたが人知れず行った良いこととは何でしょう。しかも、未だに誰にも知られず、評価されていないものはあるでしょうか。もしあるとすれば、それが聖書の御言葉に沿った行いであったなら、必ず神は報いてくださる。これは約束です。
例えば、人を愛すること。これを隠れて、誰にも知られないように行うことはできるでしょうか。施しを人に知られないように実行することは果たして可能なのでしょうか。相手がいる場合、どうすれば隠れることができるのでしょう。しかも、自分自身にも知られないように、との命令まである始末です!
主は、このことを強調されました。人々は非常に驚いた、とあるように、この約束は私たちの理解を遥かに超えています。なぜなら、隠れて善行を行えるのは、主だけだからです。
2024-07-14
6月30日「見えないものを見る」
IIコリント4:16~18
聖書は重要なことを伝えるために、二つの事柄を比較することがあります。例えば、約束の地の情報を知ったヨシュアたちとその他の人たち。また、ゴリアテと戦う直前のサウルとダビデのように。
使徒パウロは、私たちが見るべき視点を、このような聖書のルールに沿って、二つの事柄を比較しながら伝えています。「外なる人」と「内なる人」、「一時」と「永遠」そして「見えるもの」と「見えないもの」です。
パウロが伝えたかったのは、「見えないもの」を見ることでした。しかし、見えないものをどうやって見ることができるのでしょうか。
ヘブライ人への手紙の11章には、神を信じて歩んだ聖書の登場人物たちとその生涯が羅列されています。その一番最初には、こう記されています。「信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。」(ヘブライ11:1)
さらに、聖書の登場人物の歩みに先んじて、「信仰によって」という言葉が添えられているのです。彼らは、信仰によって、見えないものを見るようにして歩んだ人たちだったからです。
主イエスが十字架の上から見ていた景色は最悪でした。罵声と侮辱を浴びせる人々の内に見ていたものは何だったのでしょうか。それこそ、彼らの内にある、「見えないもの」だったのです。
2024-07-14
6月23日「自己発見型バイブルスタディ」
ヨハネ4:7~15
主イエスは井戸に水を汲みに来たサマリアの女性に語りかけます。「この水を飲む者はだれでもまた渇く。しかし、わたしが与える水を飲む者は決して渇かない。わたしが与える水はその人の内で泉となり、永遠の命に至る水がわき出る。」(ヨハネ4:13-14)
苦難や必要を感じて、この地上に井戸を探していませんか。それは一時的にはあなたを満たしてくれるでしょう。しかし、根本的な解決や真の救いの道ではないのです。
すべての必要は主イエスのもとにあり、主が与えてくださる水によらなければ、本当の必要さえ、分からないままなのです。なぜなら、主は「道であり、真理であり、命」だからです。
今日はそのことについて、共に考えてみましょう。
※プライベートな内容を含むため、動画はありません。ご了承ください。
2024-06-16
6月16日「神が見る本当のあなた」
ヨハネ7:37~39
聖書は人類の救いについて、神の計画が示された啓示の書です。その頂点は主イエスの十字架と復活と言えるでしょう。さらに、救いの恵みを知った今、聖書は救い以外にも何かしらの役割があるのでしょうか。もちろん、あるのです。
救いのメッセージを受けるだけなら、一度きりでも良いかもしれません。しかし、日々の生活の中で、聖書を開くこと、その御言葉の一つひとつを心に刻むことは、天国行きの切符を得ることと同様に重要なことです。なぜなら、それがこの地上を生きる私たちにとって、幸せに直結する内容だからです。
乾いた土地に住むイスラエルの民は、いつか救い主が与えてくれるであろう豊かな水を夢見ながら、その到来を信じ続けていました。しかし、英雄的な努力を強いられ、ルーティン化し、形骸化した信仰は、眼の前の救い主を認めることができませんでした。
その方は、信じる者に、もれなく聖霊を与えると約束されました。聖霊がもたらす実りは、天国由来のものです。しかし、聖霊が与えられているかどうか、そもそも、聖霊体験をしたことがなければ、聖霊の存在について知る由もありません。
霊の火を消してはなりません、と聖書にあるように、今ここに火がついていることを知っているでしょうか。その火は、あなたの罪を燃やし尽くし、人を新生し、神が見ておられる、本当のあなたへと導く霊なのです。
2024-06-16
6月9日「何時でも、どこでも」
列王下5:14 ヨハネ9:1~12
生まれつき目の見えない人の前を通った時、弟子たちが、「この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか。本人ですかそれとも両親ですか。」と主に尋ねました。2000年前も、今日も変わらぬ問いで、今日のわたしたちの問いでもあります。それに対して主は、「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。」と明言されます。
大学で福祉を学ぶ前から、幼い時からのわたしの内なる問いでもありました。ハンセン病の方々との出会いを通して、生涯のわたしの問いともなりました。「なぜ?何故?ナゼ?」その問いは、わたしの人生に、影のように付きまといました。それは、生きることへの問いとなり付きまといました。
人生に問いを発する、不条理を受け止めきれないわたしがいました。大学に入っても、福祉を学んでも、小さな明かりすら見えない、人生にへばりついた影でした。しかし、「神の業がこの人に現れるため」と言われる主の言葉に、「問われている自分」気づきました。自分に与えられた人生を肯定することをせず、他者に向かうことが出来ないと知らされました。主イエス様を通し、「わたしがわたし」である「貴い自分」信への道が開かれていたのです。
2024-06-02
6月2日「神の子どもとして」
マルコ10:13~16
主イエスは子どもを愛する。これは信仰者なら誰でも知っていることかもしれません。そして、誰しも自分の子ども時代を思い起こしたりするはずです。しかし、主が活動されていた時代、子どもとはどんな存在だったのでしょうか。
聖書には主に男性の系図や人数だけが記されているように、女性や子どもは頭数にも入っていません。特に、旧約聖書にはそれが顕著でしょう。しかし、まことの光である主が来られてから、変化の兆しが現れます。マタイによる福音書の系図には女性の名前があり、ルカによる福音書は女性への配慮が感じられます。そして、どの福音書にも子どもが登場します。それも、主イエスが子どもを神の国の住人としてもっともふさわしい存在として人々に価値観の変化を促しているのです。
人々が是が非でも主のもとに連れてきたかった子どもとは、一体どんな子どもたちだったのでしょう。もちろん、日本のように教育を受けることができ、保護されている対象ではありません。むしろ、日々の生活に困窮し、骨と皮だけのような状態になっている子どもは珍しくなかったことでしょう。そして、すべてのことを親権者や保護者に頼らざるを得ない。それが、この子どもたちです。
キリスト信仰の究極地点はすべて明け渡すことだと言えます。地上で得たものを何ももっていくことができない天国もまた、そのことを示していると言えます。
主は、あなたに、そんな子どものようにもっとご自身を頼ってほしいのです。
2024-06-02
5月26日「神の思い」
箴言19:21
新しい歩みが始まるこの季節ですが、人によって心持ちが大きく異なる時期と言えるでしょう。ある人にとっては思い通りになった清々しさとともに訪れる季節であり、またある人にとっては、思い通りにならなかった重苦しさとともに訪れるものでしょう。
聖書は、数千年の時を超えて、様々な人の営みを経由してきた不思議な書物です。長い歴史の中で、多くの人々の人生に多大な影響を与え続けてきた聖書は、今もなお、時を超えて変わらない真理を伝えています。つまり、思い通りにならないことは、神の御旨(神の計画)だと。
私自身を振り返ってみると、聖書に触れ、神と出会う前、思い通りにならないことで、何度も方向転換をするチャンスがありました。しかし、思い通りになるように突き進んだ結果として、与えられたものは答えのない空虚な人生でした。神を信じた今、思い通りにならないことは、もっと良いことを神が計画されていること、その計画こそ、私が私らしくいられる最善策だと分かったのです。
そういう事を言うと、神は何でもご自身の思い通りになるように、私たちを動かしているように考えるかもしれません。でも、果たしてそうなのでしょうか。
聖書が伝える歴史的事実、主イエスの十字架と復活を見れば、思い通りになることとは、どんなことなのかが分かるでしょう。
2024-06-02
5月19日 ペンテコステ記念礼拝「呼び求める声」
ローマ10:13-17
主の名を呼び求める者は救われる。これは聖書が語る真実です。そして、呼び求めるためには誰かが呼び求める対象を教えていることが大前提です。
私たちも、先に呼び求めて救われた誰かから、主なる神、生けるキリストの話を聞いたのではないでしょうか?だから、人生のどん底で、その主の名を呼び求めたのです。
結果はどうだったでしょうか。神のことを知らず、聖書も開かず、神の名前くらいしか知らなかったとしても、神は私たちの叫びに応えてくださったはずです。だから今があるのです。
教会の歴史は、あのペンテコステの日から変わることがありません。変わったことといえば、賛美の種類、礼拝形式、建物のデザイン、その他、別に変わってもいいし、極端に言えば無くてもいいものです。教会の本質は、救いが与えられ、人が変革されることです。今こそ、その本質を取り戻す時です。
そして、主の不在を嘆き、しかし御言葉の約束を信じ、叫び続けた120人ほどから始まった教会は、今もなお、人々の叫びに敏感です。なぜなら、主の名を呼び求める人の変革が起こり続けているからです。そして、その変革が見たい、という叫びを持っているのもまた、教会だからです。
あなたは教会の歴史の最前線にいる人。あなたに至るまで、星の数ほど多くの方々が叫び続けてきた景色を、あなたは見ているのです。
2024-06-02
5月12日「何時でも、どこでも」
詩編118:22~25 ローマ8:26~30
ジョン・ラスキンは、19世紀のイギリスを代表する評論家です。友人の一人の夫人が、非常に高価なハンカチを汚し、嘆いているのを見て、それを譲り受け、そのシミを用いて見事な美しい模様を描いて,婦人に返したという、有名な逸話があります。日本でも葛飾北斎にも同じような逸話があります。
わたしたちの日常は凡庸に満ちて、そんなことなど起こることはないと思っています。が、「わたしを強めて下さる方のおかげで、わたしにはすべてが可能です」(フィリピ4:13)とパウロは言います。わたしたちは自分の理解(可能性)の中にすべてを取り込み、前に進もうとしません。世界を、人生を、自分の穴の中から覗いて結論を出します。
しかし、私たちは「御手の中」にます。そして、ここで神の時を生きるように招かれています。「家造りらの捨てた石が、隅の親石となった」とあるように、神の恵みの時を生きる者とされています。
1.神様はわたしたちの嫌がる病気、苦痛をも、2.悲しみをも、3.罪をすらも 御業のために用いることがお出来になると約束しています。
山上の説教の中で、「心の貧しい人」、「悲しむ人」「義のために迫害される人」の幸いを、主は宣言されました。いつも、何処もが御手の中だからです。
※動画はありません。ご了承ください。
2024-06-02
5月5日「何を見ていますか?」
IIコリント4:16~18
聖書には、特定の法則に従って描かれる文章が存在します。同じことを短い文の中で繰り返して重要性を強調したり、2つの事象を比較して、私たちの選択を正しく導くことなどです。今回は後者でしょう。
「外なる人」と「内なる人」、また「一時の軽い艱難」と「永遠の栄光」、そして「見えるもの」と「見えないもの」です。さらに、この比較を分類すると、見えるものか、見えないものか、という2つに大きく分けられるように思えます。
本当に大事なことは目に見えないもの。どこかで聞いたことのあるフレーズは、聖書を根拠としているのです。心、魂、ことば、など。考えてみると、私たちは最新の科学を持ってしても説明のできない事柄に多く接して生きているのです。しかし、こと日本においては、見えないものは軽視されがちで、実際的なものが大切にされ続けてきました。その結果が現在の姿です。
まして、ビジョンのない民は滅びる、と聖書の神の知恵が語りかけているように、霊なる神との交わりが、私たち人間にとってどれほど大切なことなのか、知る人は少ないのです。それが、まことの平安と喜びに直結しているにも関わらず、平積みのベストセラーに手を伸ばし、父なる神に手を伸ばすことはありません。
そんな唯物的な私たちのため、神は主イエスの十字架と復活によってご自身の愛と永遠の命を歴史的事実として現されたのです。
※動画はありません。ご了承ください。
2024-06-02
4月28日「神の思い」
箴言19:21
新しい歩みが始まるこの季節ですが、人によって心持ちが大きく異なる時期と言えるでしょう。ある人にとっては思い通りになった清々しさとともに訪れる季節であり、またある人にとっては、思い通りにならなかった重苦しさとともに訪れるものでしょう。
聖書は、数千年の時を超えて、様々な人の営みを経由してきた不思議な書物です。長い歴史の中で、多くの人々の人生に多大な影響を与え続けてきた聖書は、今もなお、時を超えて変わらない真理を伝えています。つまり、思い通りにならないことは、神の御旨(神の計画)だと。
私自身を振り返ってみると、聖書に触れ、神と出会う前、思い通りにならないことで、何度も方向転換をするチャンスがありました。しかし、思い通りになるように突き進んだ結果として、与えられたものは答えのない空虚な人生でした。神を信じた今、思い通りにならないことは、もっと良いことを神が計画されていること、その計画こそ、私が私らしくいられる最善策だと分かったのです。
そういう事を言うと、神は何でもご自身の思い通りになるように、私たちを動かしているように考えるかもしれません。でも、果たしてそうなのでしょうか。
聖書が伝える歴史的事実、主イエスの十字架と復活を見れば、思い通りになることとは、どんなことなのかが分かるでしょう。
※動画はありません。ご了承ください。
2024-06-02
4月21日「ただ主の栄光のために」
フィリピ1:12~21
使徒パウロは、先々で迫害され、やがて牢獄に囚われました。そこで彼が各地の教会に伝えたのは、「喜び」でした。ですから、この手紙は「喜びの手紙」と呼ばれているのです。
しかし、牢に囚われ、自由が効かない身は、本当に喜ぶべきものだったのでしょうか。牢に囚われず、自由に宣教できる方が良いに決まっている。それが私たちの常識であり、経験則であり、願望でしょう。もちろん、パウロも人間ですから、少しはそんな事を考えたに違いありません。しかし、彼は見たのです。人間が考えうる最良の常識や経験則が打ち破られ、主の栄光が燦然と輝く事実を。
2000年にわたる教会史を紐解けば、創立50年の教会で起きたことと同じような事例があるはずです。きっと、良いことばかりが起こってハッピーだった、などと遺されている史実は皆無だと思います。しかし、そうした中でこそ、人間の力ではなく、かえって神の栄光が現されることとなり、誰一人として否定できない、神の超自然的なみわざと奇蹟、何よりも人の新生が起こってきたはずです。
今、教会には、そしてあなたには、どんなことが起こっていますか。それは、どれほど難しいものでしょう。人間には解決が困難に思えるような事態であれば、喜びましょう。そこに主が働かれるからです。
2024-04-17
4月14日「あなたの隣人は誰?」
ルカ10:25~37 ヨハネ15:13
コイノニア教育センターは、ナイロビにあるスラム・キバガレ地区の子ども、青年への教育活動(職業訓練含む)の学校として2003年に始まりました。4歳児から小中高の14年間の一貫教育を提供しています。モットーは「それでも人生にイエスと言おう」貧困などの逆境の中、大きなハンディを持った人生をも生き抜くことを意味しています。
ナイロビ市内キバガレ・スラム及び近隣の、低所得、失業家庭の親、子ども、青年たちが貧困の中から希望を持って生活向上のために、自ら意欲的に取り組むことを助け、共に新しいコミュニティー作りを推進することが目的です。
コイノニア教育センターはキリスト教の精神に基づいて運営されています。このセンターの活動に関わる人々が、自分達の生活の必要を満たすことを追い求めるだけでなく、互いに愛を持って助け合い、協力し合う関係を育てていくことを目指します。(認定NPO法人ケニア・コイノニア友の会ジャパンHPより抜粋)
2024-04-17
4月7日「キリストの体として」
詩編31:15(口語) Ⅰコリント12:27
「わたしの時は御手にあります」と、「あなたがたはキリストの体であり、また、一人一人はその部分です」。加えて、「神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを、わたしたちは知っています」の御言葉が心に鳴り響いています。
更には、「いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい」(Ⅰテサ5:16~)「あなたたちは見た。わたしがエジプト人にしたことを、また、あなたたちを鷲の翼に乗せて、わたしのもとに連れて来たことを」(出エジ19:4-5)の御言葉が繰り返し思い起こされます。
教会は、わたしたちは、「信仰の杖一本の旅枕」へと招かれていることに、改めて思い至ります。この50年、「弘前西教会」は鷲の翼に乗せられ、運ばれて今日に至りました。「御心のままに望ませ、行わせておられる神」(フィリピ2:13)に導かれての、多くの信仰の友と共に歩んだ祝福の日々でした。
今は共にいない友も数えきれません。それらの人々も、キリストの体に連なっていることを覚え、感謝し祝福を祈る日々です。思いを超えた祝福に感謝し、良き牧者に委ねることのできる幸いを感謝します。キリストの体である一人一人に感謝しつつ。
2024-04-03
3月31日「約束を信じて」
ルカ23:50~24:12
主イエスの十字架は多くの人々の人生をつくり変えてきました。そして、これからも変え続けていくことでしょう。当時も、つくり変えられた人たちがいました。
主の敵対者として登場する律法学者や議員の人々の中にも、主と出会い、十字架を前にして、信仰が確かなものとなった人々がいました。議員のヨセフ、そしてニコデモの二人が、主の遺体を引き取ったのです。
聖書では、さらっと書いてあるこの出来事は、実は大変なことで、彼らはおそらく議員と律法学者を続けていくことは困難だっただろうと思います。なぜなら、彼らの同僚のほとんどが主の敵対者であり、教会の迫害者だったからです。
そして、墓の中に主を求めていた婦人たちもまた、決意を持って墓に向かった人々でした。彼女たちが主の信奉者であると分かれば、何をされるか分かりません。それでも、彼女たちは墓に向かったのです。
十字架の出来事は、罪の赦しの自覚と信仰者の決意を促し、そこに復活のわざが起こってきました。ありえないことを、ありえると信じて生きる豊かさ。そして、消え去ることのない確かな希望。それが福音のもたらす力です。
※映像に不具合があり、動画がありません。ご了承ください。
2024-04-03
3月24日「主がお入用です」
マルコ11:1~11
主イエスは最大級の賛美をもってエルサレムに迎えられました。その姿は約束されていた王の王そのものでした。人々は信じていたものが実現した喜びに満ち溢れていたようです。その主を運んでいたのは、未だ荷物を運んだことのない子ろばでした。
子ろばは「向こうの村」につながれていました。主はそこに弟子たちを派遣し、子ろばを解き放ち、ご自身のご計画に用いられたのです。初めて主の仕事を担い、人々から歓迎され、喜ばれる主のことを、自分自身の手柄のように感じたことでしょう。そして、役目を終えると、再び「向こうの村」に戻されました。
子ろばの姿は信仰者の姿と重なるものです。先に信じた人々との出会いがあり、主の御言葉による奇跡と解放を体験し、神の国に参加して喜びにあふれ、置かれた場所で咲く。何よりも、子ろばとは力なき象徴です。能力があるから、主が用いられるのではありません。主が用いたいから、能力が与えられるのです。
王の王とは、この地上の時限的な国を導くものだと信じ、それが実現したと喜んでいる人たちの顔から笑みが失せるまでに1週間もかかりませんでした。
主はあなたの思いを遥かに超えて、あなたを用い、永遠のみ国のわざへと招かれているのです。
2024-04-03
3月17日「神の見ていること」
ヨハネ9:1-3
身体に障害を抱えていたり、何か不幸な出来事が起こるとき、それは罪の現れであると信じられてきました。生まれつき目が見えない人を見た弟子たちは、彼もまた、自身の罪か、近親者の罪の影響を受けたのだろうと考え、主イエスに尋ねました。
今回の聖書箇所には、目の見えない人に関わる多くの登場人物が出てきます。弟子たち、近所の人々、両親、ファリサイ派をはじめとするユダヤ人たちです。彼らの姿は主の姿と対象的に描かれていることにお気づきになるでしょうか?
彼の身の上について尋ねてくる弟子たちに、主は次のようにおっしゃいました。「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。」(9:3)主はこの人にこれから起こることについて語られました。しかし、他の登場人物たちは、すべて過去について話をしているのです。彼の生い立ち、生活、目の癒やされた理由や方法、モーセのことなどです。
主が人をご覧になるのは、いつでも未来についてです。あなたがどんな過去を持ち、どんな現状を過ごしているのか、その理由や経緯については、主にとってこれから起こる素晴らしいことの前触れに過ぎないのです。
2024-03-08
3月10日「勝利への道」
申命記8:1~3 マタイ4:1~11
イエス様が公生涯の初め、荒れ野で40日40夜断食され、悪魔の誘惑に遭ったことはよく知られています。あの40日になぞらえて、わたしたちはこのレント(受難節)を守るのです。主に倣うことを通し、わたしたちも勝利へと招かれています。
主が荒れ野で経験された3つの誘惑は、当時の3つの有力な団体―サドカイ人、ファリサイ人、ヘロデ党―の考えに対応するものでした。同時にこれは今日のキリスト教が対決を迫られている大きな問題と、それに対する解決の方向を示しています。
第一の、パンの問題として提出された誘惑は、宗教と経済の関係を示し、唯物的、立身出世主義からの問いです。主は「神の国と神の義をもとめる」ことの優位性を明らかにします。第二に、奇跡の問題として提出された誘惑は、いわゆるご利益宗教からの問いです。キリストに従うことは、自己中心的信心との決別が不可欠です。第三は、権威の問題で、宗教と政治の関係を示しています。目的のためには手段を選ばぬ妥協に関する、世俗主義からの問いです。それに対して、「ただ神にのみ仕えよ」と主は命じます。人生に立ちはだかる3つの誘惑に、「神の言」を武器として主は勝利されました。わたしたちの、真の人生の勝利の秘訣がここにあります。
2024-03-08
3月3日「心の奥に」
マタイ6:1~4
旧約聖書の時代から、ユダヤ人は施しをするのが当たり前になっていました。それは律法で定められていたからですが、律法とは主イエスご自身のこと。施しをするのはごく自然なことだったのです。
しかし、その素晴らしい行いが罪の世にあって歪んでくると、施しが人から評価を受ける手段となっていったのです。「すでに報いを受けている」と主がおっしゃるように、評価という報いを受けること、それ自体は悪いことではないかもしれませんが、評価が目的となってしまったり、動機になることは、神ではなく人を中心に置くことになりかねないと主は警告しているように思います。
さらに、他者からの評価が高ければ高いほど、人は傲慢になるものです。そして、傲慢さは私たちを主から切り離すものであり、まさしく主からの報いを受けられない状態だと言えるでしょう。
キリストは、神であることを捨てて、人々に仕えましたが、正当な評価を受けられない状態で十字架へと進んでいかれました。しかし、神はそのキリストの姿を最高の生き方とされました。
あなたがしたことは正当な評価を受けていないかもしれない。しかし、神だけは見ていてくれるのです。
※ビデオの音声が入っていませんでしたので削除しました。大変申し訳ありません。